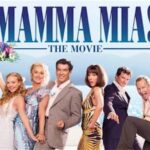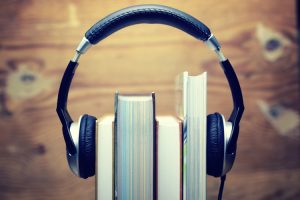1954年公開の映画『裏窓(Rear Window)』は、アルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンスの名作。主演はジェームズ・スチュワートとグレース・ケリー。
足を怪我して自宅療養するカメラマン、ジェフが窓越しに隣人たちを観察する日々。やがて「殺人事件を目撃したのでは?」と疑念を抱き、恋人リサを巻き込みながら真相を探ろうとする…。“覗く”ことそのものがテーマとなり、観客までもが共犯者のように感じさせる演出が秀逸です。
英語学習の観点では、1950年代の落ち着いた日常会話が多く、スラングが少ないため、リスニングや口語表現の教材として取り入れやすい映画です。
“We’ve become a race of Peeping Toms.”
(私たちは覗き魔の人種になってしまったわ。)
リサ(グレース・ケリー)がジェフに向かって言う有名なセリフ。
・Peeping Tom:覗き見をする人。元はイギリスの伝説に由来する俗語。比喩的に「他人のプライベートに首を突っ込む人」という意味でも使えます。
・a race of …:「〜という種族/人種」という比喩的な言い回し。
「人は誰でも他人のプライベートを覗きたがる」という皮肉を込めた、映画を象徴するセリフです。

“You don’t know the meaning of the word ‘neighbor.’”
(あなたは『隣人』って言葉の意味を分かってないわ。)
ジェフの偏った観察に対してリサが言うセリフ。
・the meaning of the word …:ある言葉の本当の意味を強調するときの定番フレーズ。簡単な表現ですが、会話の流れで聞くと強い皮肉になります。
例:You don’t know the meaning of the word ‘friendship.’(友情の意味なんて分かってないだろ)
“What people ought to do is get outside their own house and look in for a change.”
(人は外に出て、自分の家の中を見直してみるべきなのよ。)
・ought to do:「〜すべきだ」というややフォーマルな助動詞。
・for a change:「たまには」「気分転換に」。日常会話で頻出のフレーズ。
「他人を覗く前に自分自身を見つめ直すべき」という皮肉であり、映画のテーマに直結する深いセリフです。
字幕の訳し方の妙
・“Peeping Toms” → 「覗き魔」
・“the meaning of the word ‘neighbor.’” → 「隣人って言葉を知らない」
・“look in for a change.” → 「たまには自分の家を覗いてみる」
日本語字幕では直訳に近いものの、皮肉のニュアンスが柔らかめに訳されています。英語ではもっと直接的に「人を責めている」印象です。
まとめ
『裏窓』は、サスペンスでありながら「人間は他人を覗く生き物だ」という普遍的なテーマを描いた作品。
英語学習の観点では 初級〜中級者向け。
・会話はシンプルでスラングが少ない
・発音も比較的明瞭で聞き取りやすい
・短いセリフでも「比喩」や「皮肉」を学べる
“We’ve become a race of Peeping Toms.” や “look in for a change.” のように、シンプルな言葉が映画のテーマを映し出しているのが、この作品の面白さです。